日めくり万葉集 ― 2008年07月03日 18:58
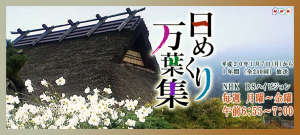
このところ、朝のNHKのBShiにハマッテいる。
午前6時55分から7時までの5分間。月曜日から金曜日までの帯番組で「日めくり万葉集」という。
「一日一首、各界を代表する選者が、万葉集をひもとき、古代に誘う」というのが、番組HPのキャッチフレーズ。これがなかなか面白い。
確かに、「万葉集は古代の人々が残したタイム・カプセル、日本の宝」に違いない。今年初めから放送された番組数は、半年を過ぎ、すでに120回を超えている。
6月の放映分だけで見ても、学校で習い、よく知られている「春過ぎて 夏来るらし 白たへの 衣干したり 天の香具山」 (持統天皇 リービ英雄)から、「へえ、こんな歌があったの……」という歌が次々。
「君に恋ひ いたもすべなみ 奈良山の 小松が下に 立ち嘆くかも」(笠女郎 金田一秀穂)▽「いさなとり 海や死にする 山や死にする 死ぬれこそ 海は潮干て 山は枯れすれ」(作者未詳 坂田明)▽「安積香山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を 我が思はなくに 」(作者未詳 香山リカ)……
選者が日替わりで、なぜその歌を選んだのかを短く説明するわけだが、なかには日ごろ名前は聞いても、馴染みのない人の場合など、初めてお目にかかる楽しみもある。また、それぞれの置かれている立場や経歴によっても、選ぶ理由はさまざまだ。
比較文化研究者の 朱捷さんは「 紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻故に 我恋ひめやも 」という大海人皇子の歌をあげ、日本人が昔から持っている「色」と「香り」との間の微妙な感覚を指摘し、
歌人の俵万智さんは「 うつそみの 人なる我や 明日よりは 二上山を 弟と我が見む 」(大伯皇女)を選んでいる。
各回の一首を、檀ふみが読み上げる。同じ一首を抑揚を変えて冒頭に2回、繰り返す。なかなか表情のある読みだ。
これまで余りなじみのない万葉集だけに、その音の響きにも驚く。伸びやかに大らかな音のつながりが、古代の日本にはあったのだ、と。
5分間という時間の長さ、もしくは短さが、本来はせわしげな朝の時間の中にあるというのが、不思議な開放感を与えてくれる。
放送予定をみていたら、なぜか7月8日の立松和平氏の分だけ、7時からの5分間になっている。
午前6時55分から7時までの5分間。月曜日から金曜日までの帯番組で「日めくり万葉集」という。
「一日一首、各界を代表する選者が、万葉集をひもとき、古代に誘う」というのが、番組HPのキャッチフレーズ。これがなかなか面白い。
確かに、「万葉集は古代の人々が残したタイム・カプセル、日本の宝」に違いない。今年初めから放送された番組数は、半年を過ぎ、すでに120回を超えている。
6月の放映分だけで見ても、学校で習い、よく知られている「春過ぎて 夏来るらし 白たへの 衣干したり 天の香具山」 (持統天皇 リービ英雄)から、「へえ、こんな歌があったの……」という歌が次々。
「君に恋ひ いたもすべなみ 奈良山の 小松が下に 立ち嘆くかも」(笠女郎 金田一秀穂)▽「いさなとり 海や死にする 山や死にする 死ぬれこそ 海は潮干て 山は枯れすれ」(作者未詳 坂田明)▽「安積香山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を 我が思はなくに 」(作者未詳 香山リカ)……
選者が日替わりで、なぜその歌を選んだのかを短く説明するわけだが、なかには日ごろ名前は聞いても、馴染みのない人の場合など、初めてお目にかかる楽しみもある。また、それぞれの置かれている立場や経歴によっても、選ぶ理由はさまざまだ。
比較文化研究者の 朱捷さんは「 紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻故に 我恋ひめやも 」という大海人皇子の歌をあげ、日本人が昔から持っている「色」と「香り」との間の微妙な感覚を指摘し、
歌人の俵万智さんは「 うつそみの 人なる我や 明日よりは 二上山を 弟と我が見む 」(大伯皇女)を選んでいる。
各回の一首を、檀ふみが読み上げる。同じ一首を抑揚を変えて冒頭に2回、繰り返す。なかなか表情のある読みだ。
これまで余りなじみのない万葉集だけに、その音の響きにも驚く。伸びやかに大らかな音のつながりが、古代の日本にはあったのだ、と。
5分間という時間の長さ、もしくは短さが、本来はせわしげな朝の時間の中にあるというのが、不思議な開放感を与えてくれる。
放送予定をみていたら、なぜか7月8日の立松和平氏の分だけ、7時からの5分間になっている。
ジャポニズム ― 2008年07月05日 23:55

上野の東京国立博物館を金曜日の夜、訪れてみた。午後8時まで開いている。
緑のライオンが2頭、入り口に伏せている表慶館で始まった「フランスが夢見た日本――陶器に映した北斎、広重」という特別展。「日仏交流150周年記念 オルセー美術館コレクション特別展」とのサブサブ・タイトルもついている。8月3日まで。
北斎漫画や広重の名所図会などに、河鍋暁斎の動物たち……。そんな日本の美を題材に、着想を得て作られたものたち。
時は19世紀末。ヨーロッパのジャポニスムに日本の浮世絵が与えた影響について、テーブルウェアに絞って展示している。パリ・オルセー美術館の所蔵作品と、東京国立博物館などの作品を対比させながら見せる、という共同企画だ。確かに、オルセーでジャポニズムの作品を、といえばついつい絵画になるから、テーブルウエアーに絞るというのは、面白い視角ではある。
出展されたテーブルウェアには2つの時代がある。初めは「セルヴィス・ルソー」と呼ばれる。陶器とガラス製品の製作販売を行っていたウジェーヌ・ルソー(1827-1890)と画家・版画家のフェリックス・ブラックモン(1833-1914)の共同製作により1866年に生まれた。葛飾北斎(1760-1849)や、《東海道五十三次》などで有名な歌川広重(1797-1858)などによる日本の作品から着想を得た作品には、ジャポニスム(日本趣味)の初期の例がみられ、このテーブルウェアはパリ万国博覧会で1867年、1878年、1898年と続けて紹介され、大成功をおさめた後、1930年代まで50年以上にわたって製作されたという。これが表慶館の右翼側の展示室に。ブラッくモンのエッチングで刷り上げたばかりのものを陶器面に転写した
ものらしい。北斎などから持ってくるものの趣味が、フランス人らしく、その配置などのセンスも好ましいものがあったのだろう。
もう一つが「セルヴィス・ランベール」。表慶館の左翼に展示されている。「セルヴィス・ルソー」がたいへん人気を博したため、1873年、ルソーは柳の下の2匹目のドジョウを狙った。セーヴル国立製陶所の装飾画家アンリ・ランベール(1836-1909)。ルソーはランベールにもジャポニスムの新たなテーブルウェアの製作を依頼する。この作品群は「セルヴィス・ルソー」と違い、手描きによる高級品で、絵画性の強いデザインが特徴です。小さいながらアンリを示すのだろう「H」のイニシャルが入れられている。手描きで現存する数が少ない「セルヴィス・ランベール」の作品は、日本初公開なのだそうだ。
表慶館のセンター奥の間には、これらのテーブルウエアーを実際にテーブルでセットアップすると、こうなる――という展示もある。
緑のライオンが2頭、入り口に伏せている表慶館で始まった「フランスが夢見た日本――陶器に映した北斎、広重」という特別展。「日仏交流150周年記念 オルセー美術館コレクション特別展」とのサブサブ・タイトルもついている。8月3日まで。
北斎漫画や広重の名所図会などに、河鍋暁斎の動物たち……。そんな日本の美を題材に、着想を得て作られたものたち。
時は19世紀末。ヨーロッパのジャポニスムに日本の浮世絵が与えた影響について、テーブルウェアに絞って展示している。パリ・オルセー美術館の所蔵作品と、東京国立博物館などの作品を対比させながら見せる、という共同企画だ。確かに、オルセーでジャポニズムの作品を、といえばついつい絵画になるから、テーブルウエアーに絞るというのは、面白い視角ではある。
出展されたテーブルウェアには2つの時代がある。初めは「セルヴィス・ルソー」と呼ばれる。陶器とガラス製品の製作販売を行っていたウジェーヌ・ルソー(1827-1890)と画家・版画家のフェリックス・ブラックモン(1833-1914)の共同製作により1866年に生まれた。葛飾北斎(1760-1849)や、《東海道五十三次》などで有名な歌川広重(1797-1858)などによる日本の作品から着想を得た作品には、ジャポニスム(日本趣味)の初期の例がみられ、このテーブルウェアはパリ万国博覧会で1867年、1878年、1898年と続けて紹介され、大成功をおさめた後、1930年代まで50年以上にわたって製作されたという。これが表慶館の右翼側の展示室に。ブラッくモンのエッチングで刷り上げたばかりのものを陶器面に転写した
ものらしい。北斎などから持ってくるものの趣味が、フランス人らしく、その配置などのセンスも好ましいものがあったのだろう。
もう一つが「セルヴィス・ランベール」。表慶館の左翼に展示されている。「セルヴィス・ルソー」がたいへん人気を博したため、1873年、ルソーは柳の下の2匹目のドジョウを狙った。セーヴル国立製陶所の装飾画家アンリ・ランベール(1836-1909)。ルソーはランベールにもジャポニスムの新たなテーブルウェアの製作を依頼する。この作品群は「セルヴィス・ルソー」と違い、手描きによる高級品で、絵画性の強いデザインが特徴です。小さいながらアンリを示すのだろう「H」のイニシャルが入れられている。手描きで現存する数が少ない「セルヴィス・ランベール」の作品は、日本初公開なのだそうだ。
表慶館のセンター奥の間には、これらのテーブルウエアーを実際にテーブルでセットアップすると、こうなる――という展示もある。
ハードル為末大 ― 2008年07月12日 15:32

陸上競技、なかでも短距離のトラック競技というのは、恵まれた体力を持つ者の独壇場なのではないか、と思ってきた。かのカール・ルイスのような抜群の筋力であるとか……。しかし、どうもそれだけではないらしい。ハードルの為末大選手。文字通りの「障碍」を飛び越え、ゴールを目指すという競技。ハードルを跳ぶという行為は、レースの中では、単にハードルを越えると言う以上に、意味のある行為であるようだ。
――NHK総合テレビで「スポーツ大陸」を見た(11日午後10時から)。
スポーツ選手という感じより、求道僧のような印象だ。
世界選手権400mハードルで、2度の銅メダルを獲得している為末選手。北京の五輪で「金」を目指す。オフィシャルサイトのプロフィールによると、身長170cm。体重66kg。日本の選手でも、身長・体重で為末を上回る選手は少なくない。世界では、さらにそうだ。その中で、為末が銅メダルを2度獲ってきたのは、何か。為末が持っているハードリング、つまりハードルをうまく跳び抜ける技術がある、ということらしい。ただ、為末は言う。「ハードルを飛び越えるための、踏み切るポイントが決まっていても、それを興奮し、緊張している状態のなかで、きちんと平常通りにできるかどうか、だ」と。できそうでいて、単なる技術というだけの勝負であるわけではなさそうだ。
このドキュメントで初めて知ったが、為末はこの競技に関して、高校を卒業した時から、いわゆる「コーチ」を持たない。自身が「コーチ」であり、選手でやってきたのだという。日々の練習のメニューも、大会への参加などについても、自身で考え、自身で決定している。「酒屋でのプロ野球談義でも、贔屓のチームがなぜ負けたのか、そして、どうしたら勝てるのか、という反省や、未来への望みについて話すこと、それこそが楽しみなのだと思う。その過去の成績についての分析をして、次の闘いのために、どのように練習のメニューを作っていくかが、一番の楽しみのはず。それを他の人に委ねてしまうのはもったいない」。反面、何かがあっても、巧くいかなかったことをコーチ初め、他者に転嫁することはできない。責任は、良くも悪くも自身で引き受けるよりしかない。
そんな中で、為末は北京での「金」のために、「ハードル」に1年間、封印をする。ハードリングでは勝てても、それからゴールまでの間で、世界の選手に「走り」で負けてしまうと、「銅=3位」でしかありえない、ということから、基本である「走り」に専念する。ハイハイを始めた甥の動きも、走りに加える試みもした。練習でもハードルを跳ばず、「走る」ことだけに専念してスピード強化に努めた。
しかし、その成果を見せるべき2007年の世界選手権で、まさかの「予選敗退」。成績は以前の自身の成績に比べても、大幅に遅いものだった。「早く走ることへの動作と、ハードルの手前で、それを跳ぶための動作というのが、同じように見えて、走っていると、逆の動きになってしまっている」と、一種の違和感まで分析した。そこにアキレス腱など足の筋肉の痛み、というアクシデント。北京五輪への予選会が刻々と近づいてくる。走れない。練習ができない。故障の回復と練習をすることとの間の相克。自身がコーチであることの一層のつらさも襲ってくる。
6月末の日本選手権。予選では通過8選手の一番ビリだった。2位までに入らなければ北京への切符は手に入らない。大方の予想は、為末に目はない、というものだった。ところが奇跡は起きた。映像では、スタート前の為末の緊張した顔を、表情をジッと追っている。その表情から、何かの作戦を立てている、という論理的なものは感じられない。むしろ獲物を狙って走り始める動物の気配だ。
為末の公式ブログ――。
レース後にレースの事を書くのが常のこのブログですが、今回の結果に関しては私自身がよくわかっていません。予選の後に冷静に分析しまして、2着だと踏んでいましたので、今日はそれを狙っていました。
2着に入らなければ五輪の候補から外れてしまいますし、とにかく最低ラインをそこに持っていきました。この状態で1着を狙うのは危なすぎると思ったからです。ミスしたらハードルにぶつけて転倒すらあるという感触がありましたから。
とにかく神経が張りつめていたので、心の余裕がありませんでした。人に会ったり談笑したりということができなかったので、ずいぶんと不躾だったかもしれません。そうだったらごめんなさい。とにかくこんなに追いつめられたのは久しぶりです。
こういう時はぶっとんでしまうのが私の癖なので、スタートから行き過ぎないようにちゃんと冷静にと心がけていました。心がけていたのですが、スタートのピストルが鳴った瞬間にとばしてしまっていて、行くな行くなと自分で抑えたんですが抑えきれず、そのまま行ってしまいました。後の事はあまり覚えていません。気がついたら10台目を越えていたのでこれでもかというぐらい頑張りました。
感情にまかせて突っ走ってしまって、結果たまたま優勝したというのが正直な実感ですが、それでもこういう事があるんだなという不思議な気持ちでもいます。
決勝に残った8人の中で一番追いつめられていて、一番緊張していたと思うのですが、最年長でそういう心境に至るという事実について、これはこれでいい事なのかなと思いました。成長しているようで成長していないのかもしれません。
とにもかくにもオリンピックに近づきました。こうやって急に追い風が吹いてくると調子に乗ってこのまま何か起きるんじゃないかと思い込んでしまうのは悪い癖です。でも、癖が悪いとは限らないというのは今日で重々わかりましたし、それが本来の姿ならそのまま行ってしまうのも悪くないなと思っています。
――格好が良すぎるかもしれない。
番組のインタビューで「ロシアン・ルーレット」の喩えを使っていた。「金メダルか実弾が、確率2分の1でも、やってみたいと思ったんですよね。そういう賭けって嫌いじゃないんです」。銅ではなく、金を狙うためには、それしかなかったかもしれない。「失敗したら、結局、なにもできなかった男、ということになるんでしょうね」とも。それだけに、足の痛みで北京へのトライアルに立てないのでは、という恐怖は強かったようだ。「ちょうど、柔道で井上康生君が引退の会見をしているのを見ましたが、ぼくも同じ側にいてもおかしくない立場ですからね」。
10代目のハードル。を跳び越えた後の直線、為末の走りのスピードは、これまでの加工曲線ではなく、より早い回転に見えた。その映像は、用意をされたシナリオに従って撮られているかのようだった。
記憶に残るドキュメンタリーとは、ドラマより、ドラマティックであるものだ。
全体には「求道僧」という印象が間違ってはいないように思えた。自身を突き放したようにすら見える冷静さ、論理立て。そういったものがなければ、恐らくは彼の自身がないのであろう、とも。だが、最後のレースでは、やはり論理ではなかったのかもしれない。「感情」というより、「情念」という言葉の方が、多分ぴったりするのだろう。
北京五輪を見る楽しみが、また一つ増えた。
http://tamesue.cocolog-nifty.com/...
――NHK総合テレビで「スポーツ大陸」を見た(11日午後10時から)。
スポーツ選手という感じより、求道僧のような印象だ。
世界選手権400mハードルで、2度の銅メダルを獲得している為末選手。北京の五輪で「金」を目指す。オフィシャルサイトのプロフィールによると、身長170cm。体重66kg。日本の選手でも、身長・体重で為末を上回る選手は少なくない。世界では、さらにそうだ。その中で、為末が銅メダルを2度獲ってきたのは、何か。為末が持っているハードリング、つまりハードルをうまく跳び抜ける技術がある、ということらしい。ただ、為末は言う。「ハードルを飛び越えるための、踏み切るポイントが決まっていても、それを興奮し、緊張している状態のなかで、きちんと平常通りにできるかどうか、だ」と。できそうでいて、単なる技術というだけの勝負であるわけではなさそうだ。
このドキュメントで初めて知ったが、為末はこの競技に関して、高校を卒業した時から、いわゆる「コーチ」を持たない。自身が「コーチ」であり、選手でやってきたのだという。日々の練習のメニューも、大会への参加などについても、自身で考え、自身で決定している。「酒屋でのプロ野球談義でも、贔屓のチームがなぜ負けたのか、そして、どうしたら勝てるのか、という反省や、未来への望みについて話すこと、それこそが楽しみなのだと思う。その過去の成績についての分析をして、次の闘いのために、どのように練習のメニューを作っていくかが、一番の楽しみのはず。それを他の人に委ねてしまうのはもったいない」。反面、何かがあっても、巧くいかなかったことをコーチ初め、他者に転嫁することはできない。責任は、良くも悪くも自身で引き受けるよりしかない。
そんな中で、為末は北京での「金」のために、「ハードル」に1年間、封印をする。ハードリングでは勝てても、それからゴールまでの間で、世界の選手に「走り」で負けてしまうと、「銅=3位」でしかありえない、ということから、基本である「走り」に専念する。ハイハイを始めた甥の動きも、走りに加える試みもした。練習でもハードルを跳ばず、「走る」ことだけに専念してスピード強化に努めた。
しかし、その成果を見せるべき2007年の世界選手権で、まさかの「予選敗退」。成績は以前の自身の成績に比べても、大幅に遅いものだった。「早く走ることへの動作と、ハードルの手前で、それを跳ぶための動作というのが、同じように見えて、走っていると、逆の動きになってしまっている」と、一種の違和感まで分析した。そこにアキレス腱など足の筋肉の痛み、というアクシデント。北京五輪への予選会が刻々と近づいてくる。走れない。練習ができない。故障の回復と練習をすることとの間の相克。自身がコーチであることの一層のつらさも襲ってくる。
6月末の日本選手権。予選では通過8選手の一番ビリだった。2位までに入らなければ北京への切符は手に入らない。大方の予想は、為末に目はない、というものだった。ところが奇跡は起きた。映像では、スタート前の為末の緊張した顔を、表情をジッと追っている。その表情から、何かの作戦を立てている、という論理的なものは感じられない。むしろ獲物を狙って走り始める動物の気配だ。
為末の公式ブログ――。
レース後にレースの事を書くのが常のこのブログですが、今回の結果に関しては私自身がよくわかっていません。予選の後に冷静に分析しまして、2着だと踏んでいましたので、今日はそれを狙っていました。
2着に入らなければ五輪の候補から外れてしまいますし、とにかく最低ラインをそこに持っていきました。この状態で1着を狙うのは危なすぎると思ったからです。ミスしたらハードルにぶつけて転倒すらあるという感触がありましたから。
とにかく神経が張りつめていたので、心の余裕がありませんでした。人に会ったり談笑したりということができなかったので、ずいぶんと不躾だったかもしれません。そうだったらごめんなさい。とにかくこんなに追いつめられたのは久しぶりです。
こういう時はぶっとんでしまうのが私の癖なので、スタートから行き過ぎないようにちゃんと冷静にと心がけていました。心がけていたのですが、スタートのピストルが鳴った瞬間にとばしてしまっていて、行くな行くなと自分で抑えたんですが抑えきれず、そのまま行ってしまいました。後の事はあまり覚えていません。気がついたら10台目を越えていたのでこれでもかというぐらい頑張りました。
感情にまかせて突っ走ってしまって、結果たまたま優勝したというのが正直な実感ですが、それでもこういう事があるんだなという不思議な気持ちでもいます。
決勝に残った8人の中で一番追いつめられていて、一番緊張していたと思うのですが、最年長でそういう心境に至るという事実について、これはこれでいい事なのかなと思いました。成長しているようで成長していないのかもしれません。
とにもかくにもオリンピックに近づきました。こうやって急に追い風が吹いてくると調子に乗ってこのまま何か起きるんじゃないかと思い込んでしまうのは悪い癖です。でも、癖が悪いとは限らないというのは今日で重々わかりましたし、それが本来の姿ならそのまま行ってしまうのも悪くないなと思っています。
――格好が良すぎるかもしれない。
番組のインタビューで「ロシアン・ルーレット」の喩えを使っていた。「金メダルか実弾が、確率2分の1でも、やってみたいと思ったんですよね。そういう賭けって嫌いじゃないんです」。銅ではなく、金を狙うためには、それしかなかったかもしれない。「失敗したら、結局、なにもできなかった男、ということになるんでしょうね」とも。それだけに、足の痛みで北京へのトライアルに立てないのでは、という恐怖は強かったようだ。「ちょうど、柔道で井上康生君が引退の会見をしているのを見ましたが、ぼくも同じ側にいてもおかしくない立場ですからね」。
10代目のハードル。を跳び越えた後の直線、為末の走りのスピードは、これまでの加工曲線ではなく、より早い回転に見えた。その映像は、用意をされたシナリオに従って撮られているかのようだった。
記憶に残るドキュメンタリーとは、ドラマより、ドラマティックであるものだ。
全体には「求道僧」という印象が間違ってはいないように思えた。自身を突き放したようにすら見える冷静さ、論理立て。そういったものがなければ、恐らくは彼の自身がないのであろう、とも。だが、最後のレースでは、やはり論理ではなかったのかもしれない。「感情」というより、「情念」という言葉の方が、多分ぴったりするのだろう。
北京五輪を見る楽しみが、また一つ増えた。
http://tamesue.cocolog-nifty.com/...
名人戦 森内俊之vs羽生善治 ― 2008年07月16日 00:47

何かの”勝ち”が見えた時、羽生の盤面に駒を差す指先が震える。これまでに活字では、その場面の再現を表現として見たが、このテレビのドキュメンタリーは、生の映像で、それを見せてくれた。
15日NHK総合 「プロフェッショナル 仕事の流儀」のドキュメンタリーだ。タイトルは「ライバルスペシャル 最強の二人、宿命の対決 名人戦 森内俊之vs羽生善治」
番組宣伝のHP に曰く――将棋界で最も伝統のあるタイトル・名人戦。今年の対局は、4期連続で名人の座を守る森内俊之(37)と挑戦者・羽生善治(37)。二人は、「宿命のライバル」、同期で同い年、小学4年生以来、27年に渡ってしのぎを削ってきた。――
NHKのドキュメンタリーの系譜の中で、今回の「プロフェッショナル」は、流れの中でちょっと異色な感じがした(私の勉強不足かもしれないが)。この番組では多く、一人のプロの技を追求していく形で、対局者のようなものについては少ないような気がしてきた。
提示されると、改めてそう思うが、若くして七冠を手にした天才肌の羽生と、その背を追いかけ、30代では「その関係」から開き直り、永世名人の地位を先に奪った森内。その二人のドラマが、ドラマとして映し出されていた。
緒戦から、一局ずつを、かなり丁寧になぞりながら、スタジオのインタビューも夫々の個人インタビューの形をとったことも、結局は成功しているようだ。
棋士が目指すのは、将棋でも囲碁でも、定石から飛翔して、最善の手を棋譜に残すこと。勿論、その前に現世的な棋戦での勝利があるにせよ、である。細かな対局の一つずつの指し手は分からないが、最善手を打ち続けていられれば、あるいは負けがない、絶対的な勝利が得られるだろう。だが、理想的な棋士であっても、やはり人間であることは間違いない。その中で、対局者も考え及ばない「一手」が飛び出す。だが、それが絶対的な優位を得るかと言えば、それだけでもない。勝負に対する「見通し」「読み」の早さは、年を追って見えてくるのだろう。だが、それだけでない「執念」からの逆転劇もある。一巡した羽生にとって、この名人戦は一つの踊り場になるのかもしれない。
常識破りの「閃き」の羽生、重厚な「受け」で相手の気持ちの揺れすら誘う森内。
かつて枡田vs大山があり、加藤一二三vs中原誠の時代もあった。「ライバル」がそれぞれの「プロフェッショナル」な部分を磨いてゆく。「相手がいなければ、ひとりでここまで来たか、来られたかというと、そうはいかなかっただろう」。切磋琢磨とは、文字通り、そうなのだろうが……
15日NHK総合 「プロフェッショナル 仕事の流儀」のドキュメンタリーだ。タイトルは「ライバルスペシャル 最強の二人、宿命の対決 名人戦 森内俊之vs羽生善治」
番組宣伝のHP に曰く――将棋界で最も伝統のあるタイトル・名人戦。今年の対局は、4期連続で名人の座を守る森内俊之(37)と挑戦者・羽生善治(37)。二人は、「宿命のライバル」、同期で同い年、小学4年生以来、27年に渡ってしのぎを削ってきた。――
NHKのドキュメンタリーの系譜の中で、今回の「プロフェッショナル」は、流れの中でちょっと異色な感じがした(私の勉強不足かもしれないが)。この番組では多く、一人のプロの技を追求していく形で、対局者のようなものについては少ないような気がしてきた。
提示されると、改めてそう思うが、若くして七冠を手にした天才肌の羽生と、その背を追いかけ、30代では「その関係」から開き直り、永世名人の地位を先に奪った森内。その二人のドラマが、ドラマとして映し出されていた。
緒戦から、一局ずつを、かなり丁寧になぞりながら、スタジオのインタビューも夫々の個人インタビューの形をとったことも、結局は成功しているようだ。
棋士が目指すのは、将棋でも囲碁でも、定石から飛翔して、最善の手を棋譜に残すこと。勿論、その前に現世的な棋戦での勝利があるにせよ、である。細かな対局の一つずつの指し手は分からないが、最善手を打ち続けていられれば、あるいは負けがない、絶対的な勝利が得られるだろう。だが、理想的な棋士であっても、やはり人間であることは間違いない。その中で、対局者も考え及ばない「一手」が飛び出す。だが、それが絶対的な優位を得るかと言えば、それだけでもない。勝負に対する「見通し」「読み」の早さは、年を追って見えてくるのだろう。だが、それだけでない「執念」からの逆転劇もある。一巡した羽生にとって、この名人戦は一つの踊り場になるのかもしれない。
常識破りの「閃き」の羽生、重厚な「受け」で相手の気持ちの揺れすら誘う森内。
かつて枡田vs大山があり、加藤一二三vs中原誠の時代もあった。「ライバル」がそれぞれの「プロフェッショナル」な部分を磨いてゆく。「相手がいなければ、ひとりでここまで来たか、来られたかというと、そうはいかなかっただろう」。切磋琢磨とは、文字通り、そうなのだろうが……
祖国ポーランド ― 2008年07月17日 07:44

ヨーロッパの中でも、ポーランドという国の歩みは、波乱に富んでいる。そのポーランドを祖国に持つ人にとっては、波乱どころではない恐るべき歴史に弄ばれた、悲劇であるかもしれない。ドイツとソ連の密約の中で、祖国は引きちぎられ、国の名前もなくなり、親が虐殺をされたことも。その歴史がなければ、アンジェイ・ワイダの作品はなかったのかもしれない。「ハイビジョン特集 映画監督アンジェイ・ワイダ ~祖国ポーランドを撮り続けた男~」(NHK BShi の7月13日(日) 午後7:00~8:50)を見て、そう思った。
特集は、第二次大戦中にポーランドの将校が大虐殺された、いわゆる「カチンの森」事件を描いた、映画「カチン」の試写会の場面から始まった。この事件、旧ソ連の犯行にもかかわらず、ソ連はその真相をゴルバチョフが認めるまでの長い間封印し、ポーランドではそれに触れることがタブーだった。民主化されてなんと20年近く経った今、やっと完成した。その会場でワイダは「私はこの映画を両親に捧げる。私は運命として人生の最後にカチンを撮った」と発言した。
ワイダの父親も将校として、この事件の犠牲になっていた。
1939年9月1日、ドイツ軍とドイツと同盟したスロヴァキアの軍部隊が、さらに9月17日にソ連軍がポーランド領内に武力侵攻した。ドイツのポーランド侵攻作戦はソ連外相モロトフとドイツ外相リッベントロップの独ソ不可侵条約調印の一週間後のこと。ワイダが13歳の時、これが父親との別れになる。1943年、ソ連に侵攻したドイツ軍はカティン近くの森で溝に4,000人以上のポーランド軍将校・警察官・公務員・元地主等の遺体が埋められているのを発見する。ドイツは、「ソ連が彼らを裁判無しで虐殺した」として非難。一方、ソ連及び赤軍はドイツの主張に「1941年に侵略してきたドイツ軍によって戦争捕虜のポーランド人たちは捕らえられ、殺害された」と反論・主張した。
事件の真相は、冷戦の波のまにまに隠される。失地回復したソ連は1944年にカティンの森を再調査し、死体を再び掘り起こした。1946年、ニュルンベルク裁判においてソ連の検察官はカティンの森での虐殺についてドイツを告発した。彼は「もっとも重要な戦争犯罪の内の一つがドイツのファシストによるポーランド人捕虜の大量殺害である。」と述べている。アメリカとイギリスがこの告発を支持しなかったので、カティンの森事件についてはニュルンベルク裁判では一言も述べられていない。この事件の責任が誰にあるのかについては西側でも東側においても議論が続けられたが、ポーランド統一労働者党の幹部たちはこの事件についてソビエト連邦に遠慮してか真相を究明しようとはしなかった。この状態は1989年にポーランドの共産主義政権が崩壊するまで継続した。
カチンの森事件の流れは、そのようなことなのだが、ドキュメンタリーのフィルムの中でワイダが語ったのは、そんな「歴史」ではない、もっと生な話だった。終戦前後の調査の中で、犠牲になった人たちの名前が何度にも渡って、発表されている。ちょっと違うかもしれないが「尋ね人」のカチン版。名前がない方が良い「尋ね人」だ。ワイダの母親と、父親の母、つまりワイダの祖母が、発表のあるたびに、そこに父親の名前がありはしないか、と不安の中、走り回り、そこに名前のないことで、そのつど胸を撫で下ろしていた。ワイダは、その母たちの姿を見て、カチンの森の被害者の親族の心情を身近に見ていた、と。「これを映画にするのだ」。
ワイダは終戦後、美術を志してクラクフの大学に進むが、進路を替えウッチ映画大学に進学。映画作りの道へはいっていく。ウィキペディアは次のように記す。「1954年、『世代』にて映画監督デビュー。1956年の『地下水道』がカンヌ国際映画祭審査員特別賞に輝いた。1958年の『灰とダイヤモンド』は、反ソ化したレジスタンスを描いており、象徴的表現を多用した鮮やかな描写は西側でも高い評価を受け、ヴェネチア国際映画祭批評家連盟賞を受賞した。これら三作品は、ワルシャワ蜂起時のレジスタンスや、戦後共産化したポーランド社会におけるその末路を描いており、『抵抗三部作』として知られている。」
検閲を受けてでしか、映画制作ができない中で、民族の「記憶」を、それも現在の視聴者に、どのように伝えるか――。そんな重いテーマに向かい合って、アンジェイ・ワイダの作品が出来上がってきたことが、2時間近い特集の中で理解ができた。検閲を、いかにかいくぐって、観客にその時代と民族の「記憶」を感じさせることができるのか、だ。
番組では、「灰とダイヤモンド」、「大理石の男」など数多い映画でポーランドの激動する戦後を、当局の検閲を潜り抜けながら懸命に映画を撮りつづけたワイダの証言を軸に、クラコフのワイダ・アーカイブに秘蔵されていた「検閲議事録」、「手帳」、「絵コンテ」などの未公開資料が紹介された。
「カチン」が撮られ、公開されたいま、改めてワイダの作品を振り返ってみると、ワイダの視点と手法は一貫しているように見える。例えば1977年の作品、「大理石の男」は映画学校の生徒アフニェシカが、1950年代の労働英雄の姿をテーマに卒業映画を作ろうとしていて、博物館の倉庫でかつての労働英雄ビクルートの彫像を発見、ビクルートの当時の状況やその後を知ろうと関係者への聞き込みを行うことで物語が展開する。関係者から取材をしたビクルートの話は、労働者の彫像として振りまわされた悲劇や、ビクルートが同僚をかばったがために刑務所へ送られ、妻とも別れさせられたという事実だった。しかし、アフシェニカが1950年代の状況を探ることで政府からにらまれることを忌避する上司は、ビクルート本人を見つけられなかったことを理由に撮影自体の中止を命じる。アフシェニカはそのことで失望するも父親の、カメラがなくても本人を見つけるべきだとの言葉に打たれ、ビクルートの息子に会う。息子は父親が死んだことを告げ、諦めるよう伝えた。しかし、アフシェニカは息子を説得し、息子とともにワルシャワの放送局に向かうのだった。(この項、ウィキペディア)
ワイダ自身が明らかにした「カチン」の事件についての取材、映像化への道のりは、この大理石の男のストーリーと酷似している。ワイダの父親の消息についての、情報が寄せられ、カチンで殺されたことへの確信を深めていく。
どのように「記憶」を観客に訴えていくのか、についての話では、「地下水道」のラストシーンについて、米国の記者が「あれは状況についての暗喩か」と問う。少なくとも、質問した記者には、それが「事実を伝える記憶」であることが、理解できなかった。つまり、「地下水道」では、ワルシャワの蜂起が悲劇的な終末を迎える、その時に、水道の出口から河を隔てた対岸には、蜂起軍を応援すべくいるはずだったソ連軍が、蜂起軍のみならずポーランドの国民の希望を裏切る形で、状況を見送っていた。やがて自分たちが征服者として入っていくに当たって、自分たちにとっても面倒な反抗者を見殺しにする形で、始末されるのを見過ごしているような。ポーランドの民衆は、そのことを知っている。それは「現在」でもあるのだから、ということなのだろう。
ちょっと調べ始めると、もう一枚、さらに一枚と、歴史と言われる事実の裏に、さらにそれを動かしていた歴史が垣間見えるようで、何と暗く、重いポーランドという国の歴史なのだろう、と思ってしまう。
特集とは逸れる部分はあるが、そんな歴史の中で、グダニスクを起点とした労働者の組織「連帯」が、一瞬の希望の光を与えた。私個人の記憶としては、その「連帯」の中心にいたワレサが日本にやって来た時のことを思い出す。一行は東京から関西への旅をしていた。京都に入ったその朝、ポーランド出身のローマ法王が狙撃された。結果から言えば、命には別状がなく、その後もパパがポーランドや連帯の活動と絡んでいくのだが、狙撃の一報を聞いたワレサ一行が河原町三条の教会に急ぎ、法王の無事を祈っていた姿は、その緊張と不安を膨らませた表情と共に、記憶に残っている。
その「連帯」にも、栄光と反動の波が寄せては返した。1988年の年を過ぎ、社会主義の陣営が崩壊して、初めてワイダにも「カチン」が返って来た。
どうも、まだ未整理な思いがあるが、特集としては非常に刺激的で、興味深いものであった。
特集は、第二次大戦中にポーランドの将校が大虐殺された、いわゆる「カチンの森」事件を描いた、映画「カチン」の試写会の場面から始まった。この事件、旧ソ連の犯行にもかかわらず、ソ連はその真相をゴルバチョフが認めるまでの長い間封印し、ポーランドではそれに触れることがタブーだった。民主化されてなんと20年近く経った今、やっと完成した。その会場でワイダは「私はこの映画を両親に捧げる。私は運命として人生の最後にカチンを撮った」と発言した。
ワイダの父親も将校として、この事件の犠牲になっていた。
1939年9月1日、ドイツ軍とドイツと同盟したスロヴァキアの軍部隊が、さらに9月17日にソ連軍がポーランド領内に武力侵攻した。ドイツのポーランド侵攻作戦はソ連外相モロトフとドイツ外相リッベントロップの独ソ不可侵条約調印の一週間後のこと。ワイダが13歳の時、これが父親との別れになる。1943年、ソ連に侵攻したドイツ軍はカティン近くの森で溝に4,000人以上のポーランド軍将校・警察官・公務員・元地主等の遺体が埋められているのを発見する。ドイツは、「ソ連が彼らを裁判無しで虐殺した」として非難。一方、ソ連及び赤軍はドイツの主張に「1941年に侵略してきたドイツ軍によって戦争捕虜のポーランド人たちは捕らえられ、殺害された」と反論・主張した。
事件の真相は、冷戦の波のまにまに隠される。失地回復したソ連は1944年にカティンの森を再調査し、死体を再び掘り起こした。1946年、ニュルンベルク裁判においてソ連の検察官はカティンの森での虐殺についてドイツを告発した。彼は「もっとも重要な戦争犯罪の内の一つがドイツのファシストによるポーランド人捕虜の大量殺害である。」と述べている。アメリカとイギリスがこの告発を支持しなかったので、カティンの森事件についてはニュルンベルク裁判では一言も述べられていない。この事件の責任が誰にあるのかについては西側でも東側においても議論が続けられたが、ポーランド統一労働者党の幹部たちはこの事件についてソビエト連邦に遠慮してか真相を究明しようとはしなかった。この状態は1989年にポーランドの共産主義政権が崩壊するまで継続した。
カチンの森事件の流れは、そのようなことなのだが、ドキュメンタリーのフィルムの中でワイダが語ったのは、そんな「歴史」ではない、もっと生な話だった。終戦前後の調査の中で、犠牲になった人たちの名前が何度にも渡って、発表されている。ちょっと違うかもしれないが「尋ね人」のカチン版。名前がない方が良い「尋ね人」だ。ワイダの母親と、父親の母、つまりワイダの祖母が、発表のあるたびに、そこに父親の名前がありはしないか、と不安の中、走り回り、そこに名前のないことで、そのつど胸を撫で下ろしていた。ワイダは、その母たちの姿を見て、カチンの森の被害者の親族の心情を身近に見ていた、と。「これを映画にするのだ」。
ワイダは終戦後、美術を志してクラクフの大学に進むが、進路を替えウッチ映画大学に進学。映画作りの道へはいっていく。ウィキペディアは次のように記す。「1954年、『世代』にて映画監督デビュー。1956年の『地下水道』がカンヌ国際映画祭審査員特別賞に輝いた。1958年の『灰とダイヤモンド』は、反ソ化したレジスタンスを描いており、象徴的表現を多用した鮮やかな描写は西側でも高い評価を受け、ヴェネチア国際映画祭批評家連盟賞を受賞した。これら三作品は、ワルシャワ蜂起時のレジスタンスや、戦後共産化したポーランド社会におけるその末路を描いており、『抵抗三部作』として知られている。」
検閲を受けてでしか、映画制作ができない中で、民族の「記憶」を、それも現在の視聴者に、どのように伝えるか――。そんな重いテーマに向かい合って、アンジェイ・ワイダの作品が出来上がってきたことが、2時間近い特集の中で理解ができた。検閲を、いかにかいくぐって、観客にその時代と民族の「記憶」を感じさせることができるのか、だ。
番組では、「灰とダイヤモンド」、「大理石の男」など数多い映画でポーランドの激動する戦後を、当局の検閲を潜り抜けながら懸命に映画を撮りつづけたワイダの証言を軸に、クラコフのワイダ・アーカイブに秘蔵されていた「検閲議事録」、「手帳」、「絵コンテ」などの未公開資料が紹介された。
「カチン」が撮られ、公開されたいま、改めてワイダの作品を振り返ってみると、ワイダの視点と手法は一貫しているように見える。例えば1977年の作品、「大理石の男」は映画学校の生徒アフニェシカが、1950年代の労働英雄の姿をテーマに卒業映画を作ろうとしていて、博物館の倉庫でかつての労働英雄ビクルートの彫像を発見、ビクルートの当時の状況やその後を知ろうと関係者への聞き込みを行うことで物語が展開する。関係者から取材をしたビクルートの話は、労働者の彫像として振りまわされた悲劇や、ビクルートが同僚をかばったがために刑務所へ送られ、妻とも別れさせられたという事実だった。しかし、アフシェニカが1950年代の状況を探ることで政府からにらまれることを忌避する上司は、ビクルート本人を見つけられなかったことを理由に撮影自体の中止を命じる。アフシェニカはそのことで失望するも父親の、カメラがなくても本人を見つけるべきだとの言葉に打たれ、ビクルートの息子に会う。息子は父親が死んだことを告げ、諦めるよう伝えた。しかし、アフシェニカは息子を説得し、息子とともにワルシャワの放送局に向かうのだった。(この項、ウィキペディア)
ワイダ自身が明らかにした「カチン」の事件についての取材、映像化への道のりは、この大理石の男のストーリーと酷似している。ワイダの父親の消息についての、情報が寄せられ、カチンで殺されたことへの確信を深めていく。
どのように「記憶」を観客に訴えていくのか、についての話では、「地下水道」のラストシーンについて、米国の記者が「あれは状況についての暗喩か」と問う。少なくとも、質問した記者には、それが「事実を伝える記憶」であることが、理解できなかった。つまり、「地下水道」では、ワルシャワの蜂起が悲劇的な終末を迎える、その時に、水道の出口から河を隔てた対岸には、蜂起軍を応援すべくいるはずだったソ連軍が、蜂起軍のみならずポーランドの国民の希望を裏切る形で、状況を見送っていた。やがて自分たちが征服者として入っていくに当たって、自分たちにとっても面倒な反抗者を見殺しにする形で、始末されるのを見過ごしているような。ポーランドの民衆は、そのことを知っている。それは「現在」でもあるのだから、ということなのだろう。
ちょっと調べ始めると、もう一枚、さらに一枚と、歴史と言われる事実の裏に、さらにそれを動かしていた歴史が垣間見えるようで、何と暗く、重いポーランドという国の歴史なのだろう、と思ってしまう。
特集とは逸れる部分はあるが、そんな歴史の中で、グダニスクを起点とした労働者の組織「連帯」が、一瞬の希望の光を与えた。私個人の記憶としては、その「連帯」の中心にいたワレサが日本にやって来た時のことを思い出す。一行は東京から関西への旅をしていた。京都に入ったその朝、ポーランド出身のローマ法王が狙撃された。結果から言えば、命には別状がなく、その後もパパがポーランドや連帯の活動と絡んでいくのだが、狙撃の一報を聞いたワレサ一行が河原町三条の教会に急ぎ、法王の無事を祈っていた姿は、その緊張と不安を膨らませた表情と共に、記憶に残っている。
その「連帯」にも、栄光と反動の波が寄せては返した。1988年の年を過ぎ、社会主義の陣営が崩壊して、初めてワイダにも「カチン」が返って来た。
どうも、まだ未整理な思いがあるが、特集としては非常に刺激的で、興味深いものであった。
最近のコメント